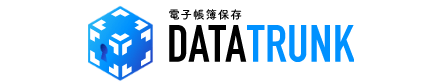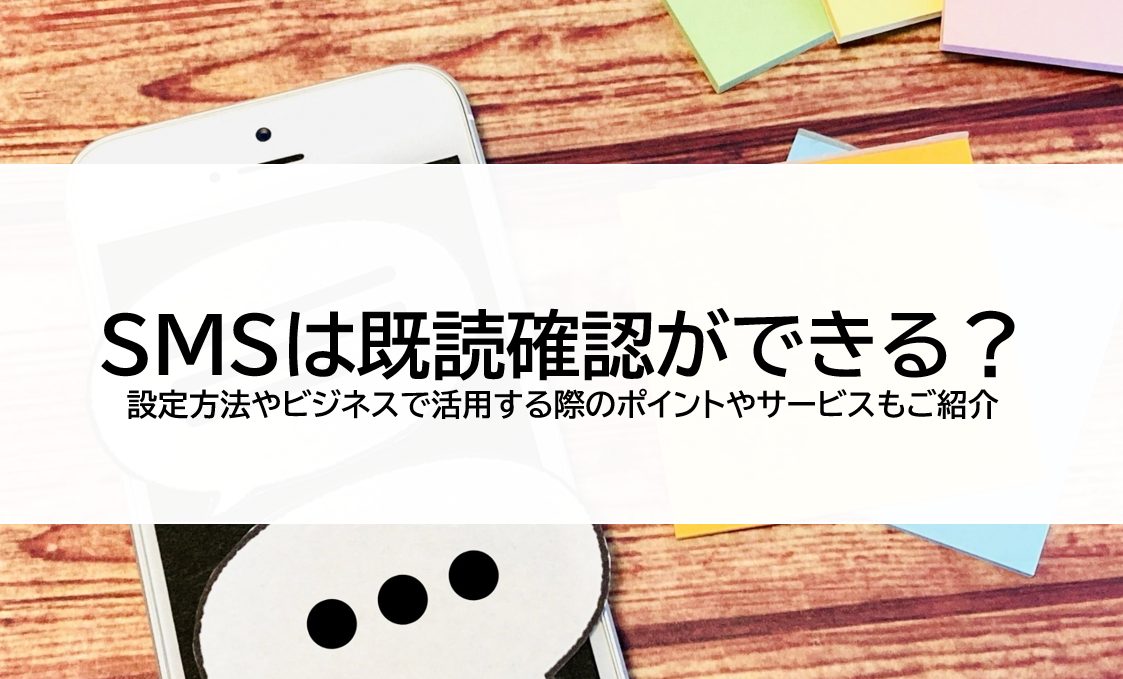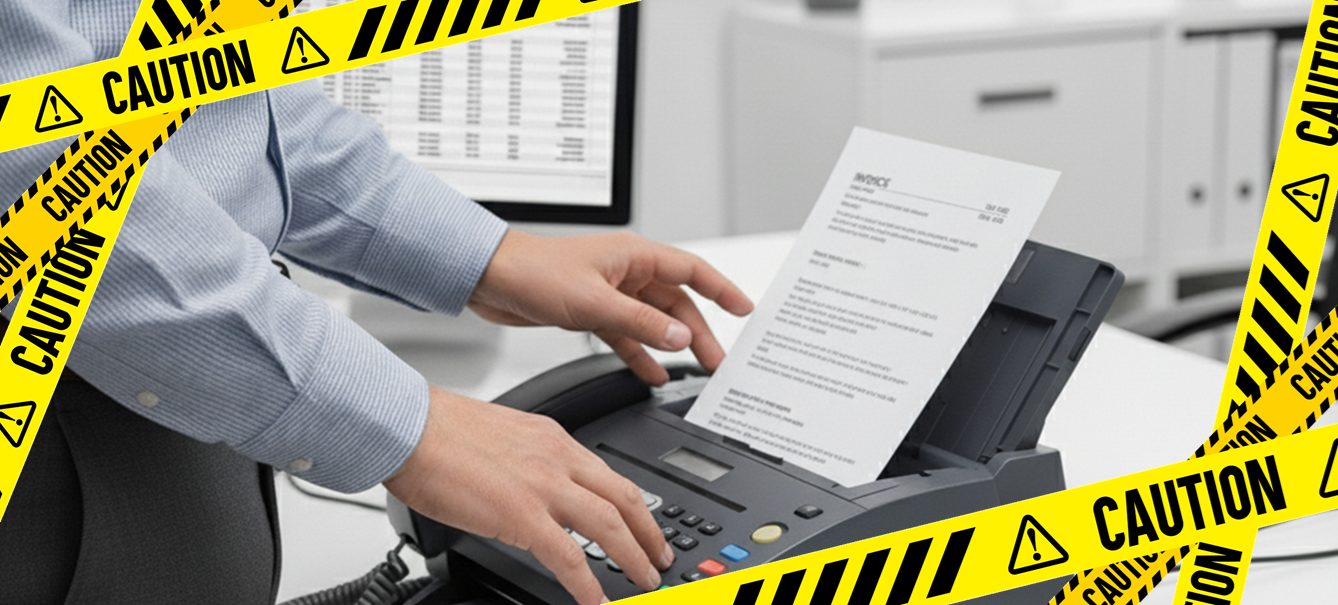
企業間の取り引きでは、日常的に行われている見積書や請求書などの帳票書類のやりとり。
最近では電子メールや電子請求書など、デジタルデータでのやり取りが増加している一方、いまだにFAXによる授受も根強く利用されています。
とくに中小企業や公共機関などとの取り引きにおいては、FAXがスタンダードであるケースも少なくありません。
本コラムでは、請求書や見積書をFAXで送る際に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
FAXで送ることは問題ないのか?
請求書や見積書をFAXで送ること自体は法的に問題ありません。FAXは電送記録が残り、相手に迅速に書類を届けられる手段として長らく利用されてきました。
多くの企業がFAXを受信手段として整備しているため、ある程度の信頼性が確保されています。
ただし、FAXには誤送信による情報漏洩のリスクが少なからずあり、個人情報や機密性の高い取引情報を含む請求書や見積書を送る際には慎重な対応が求められます。
また、書類の送付をFAXだけで完結するのではなく、原本の郵送や電子データとの併用が必要な場合があります。
なぜFAXで送ることが必要なのか
近年のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)が浸透してきているにも関わらず、FAXの使用が続く背景にはいくつかの理由があります。
相手先がFAXを主な受信手段としている
とくに中小企業や製造業、建設業界などではFAXを業務インフラの一部として利用しているケースが多く、取り引き相手の環境や要望によってFAXでの運用を選択せざるを得ない場合があります。
紙での証憑管理を求められる場合がある
電子帳簿保存法が施行された今でも一部の企業では、帳票類を紙ベースで管理・保管するルールが根強く残っています。
FAXで送られてくる帳票はそのまま保存しやすいため、依然として重宝されています。
即時性の高さ
インターネット環境やシステムに依存せず、即座に相手に書類を届けられるという点で、FAXは他の手段とくらべて一定の優位性を持ち続けています。
FAXで書類を送る際の注意点
請求書や見積書などの帳票書類をFAXで送る際には、実務的な注意点がいくつかあります。
これらを押さえることで、誤送信やトラブルの防止に繋がります。
事前に許諾を取る
当たり前のことですが、FAXで書類を送る前に相手先に「書類をFAXで送っても良いか」を確認することが必要です。
無断でFAX送信すると、受信側の運用に支障をきたすことがあるほか、情報漏洩のリスクも高まります。
とくに請求書など金銭のやり取りに関わる帳票は、相手が受け取れる日時、送信先の部署名や担当者名、送信先のFAX番号などについても確認しておきましょう。
誤送信に注意する
FAXの送信時に最も多いトラブルのひとつが「誤送信」です。
番号の入力ミスや、複数の送信先がある場合の誤選択によって、取り引きとは関係ない第三者に価格や送信先名など、重要な情報が送られてしまいます。
そうなってしまうと会社の取り引きの継続にも支障をきたしてしまいます。
FAX番号を入力する際は「目視による確認」「ダブルチェック」など、社内の送信ルールを整備しておきましょう。
送付状を付けて送る
見積書や請求書をFAXで送信する際には、必ず送付状(FAX送信表)を添付しましょう。
送付状には以下の情報を明記するのが望ましいです。
- 宛先企業名・担当者名
- 送信者の氏名・連絡先
- 送付日・送信枚数
- 送信内容の概要(例:「請求書1通」など)
送付状があることで、受信者は誰から何の書類が届いたのかをすぐに把握でき、誤認や見落としの防止につながります。
また、近年はインターネットFAXサービスを利用する企業も増えており、いくつかのサービスでは送付状のテンプレート機能が備わっています。
クラウド上で帳票をアップロードし、あらかじめ設定した送付状を添えてFAX送信できるため、紙ベースでの作業よりも効率的に運用できます。
特に見積書や請求書を毎月定型的に帳票を送るケースでは、インターネットFAXの送付状機能を活用することで、作業の省力化とミス防止が図れます。
履歴管理をできるようにする
FAXで帳票類を送った履歴を管理することも重要です。送信控えや送信レポートを出力して保管する、FAX機の送信履歴を定期的にバックアップするなどの仕組みが求められます。
また、こちらもインターネットFAXを活用すれば、送信履歴や受信記録がクラウド上に自動的に保存・管理されるため、紙ベースでの管理に比べて格段に効率的ですし、送信日時や宛先、添付ファイルの内容などもまとめて記録されるため、検索性にも優れており、監査への対応や内部統制の強化にもつながります。
会計監査や取引先とのトラブルが発生した際に、「いつ」「誰に」「何を」送ったかを証明するための根拠として役立つだけでなく、過去のやり取りを簡単に確認できることも大きなメリットです。
FAX送信後のフォローコール
FAX送信後は、相手に「無事届いたかどうか」の確認を行いましょう。
送信ミスや紙詰まり、受信トラブルなどがあった場合、相手が気づかないまま期日が過ぎてしまうという事態もあり得ます。
フォローコールは、送信後すぐ行うのが理想的です。とくに請求書などの重要書類の場合、確認の一言が取引相手の信頼感にも繋がります。
原本を郵送する
FAXはあくまで「写し(コピー)」であり、正式な帳票の「原本」ではありません。印鑑が必要な請求書や、契約書など法的効力が求められる書類については、後日原本を郵送することが一般的です。
この際、郵送日や郵送手段(普通郵便・書留など)も明確にし、トラブルを避けましょう。
また、請求書の場合、PDFなどの電子データを送付するケースも増えているため、FAX送信前に郵送or電子データの送付かを取引先に事前に確認しておく必要があります。
原本の管理
送付した帳票類の原本は、社内で厳重に保管する必要があります。スキャンしてデジタル保存するとともに、紙の原本も一定期間保存することで、税務調査や取引履歴の確認時に対応できます。
帳票の種類ごとに保存期間を設定し、管理台帳を整備するなど、帳票管理体制を構築しておくと良いでしょう。
電子帳簿保存についても確認をする
2024年に施行された改正電子帳簿保存法により、帳票類の電子保存に関する要件が見直され、FAXについても企業の対応が求められるようになっています。
FAXで送信した見積書や請求書を電子データ化して保存する場合にも、法的要件を満たす必要があります。
電子帳簿保存法への対応は、社内のITシステムとの連携や、業務フローの見直しを伴う場合もあるため、早めの検討が重要です。
まとめ
請求書や見積書といった帳票書類をFAXで送ることは、即時性や相手の受け取りやすさなどのメリットがあり、今でも多くの企業にとって有効な手段です。
しかしその一方で、FAXならではの課題である誤送信や情報漏洩などのリスクにも注意を払わなければなりません。
送信前の許諾や送付状の添付、送信後のフォロー、そして原本管理までを含めた一連の業務フローを整備することが、信頼性の高い帳票の運用には必要です。
また、改正されるたびに要件が緩和されている電子帳簿保存法への対応も必要です。今まで行ってきたFAXでの運用と併用しつつ、将来的なデジタル化への備えも並行して行うべきです。
FAXのメリットと電子取引のメリットを上手く使い分け、効率的かつ安全な運用を実現しましょう。