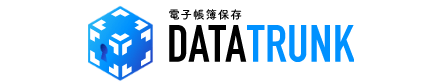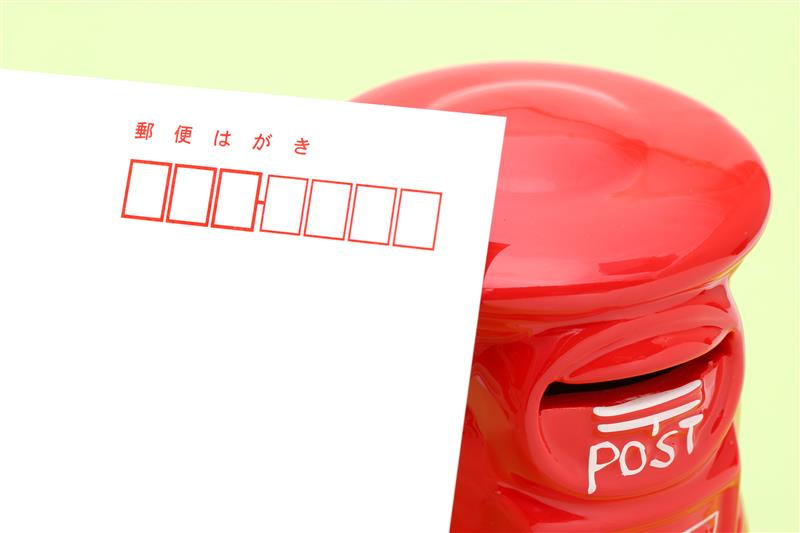地震や台風による大雨、大雪などの災害が発生した際、まずしなければならないのは状況の把握と関係者の安否確認。通信の輻輳を防ぐため、災害地域への不要不急の連絡は控えるべきですが、関係者や取引先の状況把握は重要です。
そのような事態に使えるのが、SMSを利用した安否確認連絡です。
この記事では、安否確認の際に役立つSMSのポイントについて解説していきます。
電話・メールを使った緊急連絡
今や国民1人につき1台以上所持していると言われている携帯電話。
災害地域にいる相手の状況を確認するには電話をかけるのが無難でしょう。しかし大規模な災害発生時には被災地域への電話が集中します。
さらに警察・消防への緊急通報などの重要性の高い通話が優先されるため、被災地域へ電話は平時よりもはるかに繋がりにくくなります。実際、総務省の発表によると、東日本大震災の発生時、被災地域付近の音声通話が通常の50~60倍に達したという報告も出ています。(引用元はこちら)
また被災地域の方が電話に出られない状況にいる、携帯電話のバッテリーを温存したいため電話を控えたいなどの場合もあります。
電話がだめなら携帯メールの場合はどうでしょうか。
メールで使うパケット通信は電話に比べてアクセスが集中しにくく、届きやすいという特長があります。
しかしメールアドレスは変更が簡単にできるだけでなく、複数所有される方も多くいます。アドレスが変わりメールが届かない場合や、メインのアドレスに届かず確認が遅れることもあります。
いつ来るかわからない災害のために常時準備をしておくことは重要ですので、到達率を上げるためにはメールアドレスの定期的な確認・管理と、受信者側での設定が必要不可欠です。
そして会社運営においても、緊急時の従業員やその家族、取引先などへの連絡手段を確保しておくことは非常に重要で、BCP(事業継続計画)の重要な要素のひとつです。
SMSの特徴を活かせば適切な安否確認が可能!
災害発生地域にいる人と連絡が付きづらいという課題を解決できるのがSMSです。
SMSはキャリアが違ってもメッセージのやりとりができるのが特長です。SMSは企業利用の用途も広がり、2016年には約2億2,460万通だった送信件数が2021年には約26億8,800万通にまで拡大しています。
以下のようなSMSの特徴・メリットを利用することで、安否連絡をスムーズに行えます。
SMSは災害時に強い通信手段
SMSは電話と同じ回線交換方式でメッセージを送信しますが、音声通話時に使用する「トラフィックチャネル」ではなく「信号線」や「シグナリングチャネル」で送信されるため、一般的に電話より繋がりやすいと言われています。そのため、通信規制の影響を受けにくいSMSは災害時にも有効な通信手段と言えます。
携帯電話番号に直接届く
SMSは、相手の携帯電話番号さえわかればメッセージを送ることができます。携帯電話番号はメールアドレスと違い、2006年に開始されたMNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ)制度により、電話番号を変えずに利用し続けることができるためメールに比べて到達率が高い傾向にあります。
古いメールアドレスしか分からず迅速な連絡ができない、といった事態を防ぐことができます。
アプリのインストールが不要
LINEなどのアプリケーションと違い、SMSは携帯電話番号に標準で備わっている機能です。(※格安SIMの場合は契約プランなどによってSMSが利用できないことがありますのでご注意ください)
事前のインストールや設定が不要となるので、相手の状況に左右されずメッセージを送ることができるツールだと言えます。
到達率・開封率に優れている
SMSは受信すると携帯に受信したことがポップアップで表示されるため、受信者はメッセージが届いたことに気づきやすく、確認されやすい仕様です。変更されにくい携帯電話番号に直接送信できることとあわせて、メールに比べメッセージの開封率は10倍以上とも言われています。
災害時は仕事の関係者やプライベートの友人など、1人に対して大量の安否連絡が届きます。SMSなら電話と違ってすぐに対応する必要がないので、落ち着いたタイミングでメッセージを見てもらうことができます。
企業の安否確認や緊急連絡にはSMS一斉送信サービスがおすすめ
SMSは携帯電話番号だけでメッセージのやりとりができる使い勝手のいいサービスではありますが、複数の人に同時に送れません。個人間のやりとりでは困ることはありませんが、企業で安否確認連絡を個別に送るとなると、大きな工数がかかります。
SMS送信サービスは、宛先リストさえあれば、同じメッセージを一斉に送信できる仕組みです。一度に数千人の携帯電話番号への送信でも1回の操作で終えることができるため、安否確認や緊急連絡に向いています。
SMS一斉配信後にメッセージが届いたかどうか分かる
SMSにはメッセージアプリのような「既読機能」はありませんが、SMS一斉配信サービスには、メッセージ内に差し込んだURLのクリック状況が確認できる「トラッキング機能」があります。このトラッキング機能を活用することで送信者側は「誰が、いつメッセージを確認したか」を、受信した人は自身のタイミングで安否を報告できるようになります。
まとめ
このように、SMSは緊急連絡や安否確認に非常に有効です。また、SMS送信サービスは「本人認証」や「リマインド」など、災害対策以外にも様々な用途で活用されています。当社ではオンライン相談やウェビナーなどでその活用方法をご紹介しております。ご興味がございましたら是非ご相談ください。