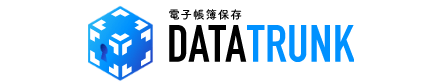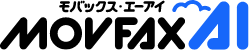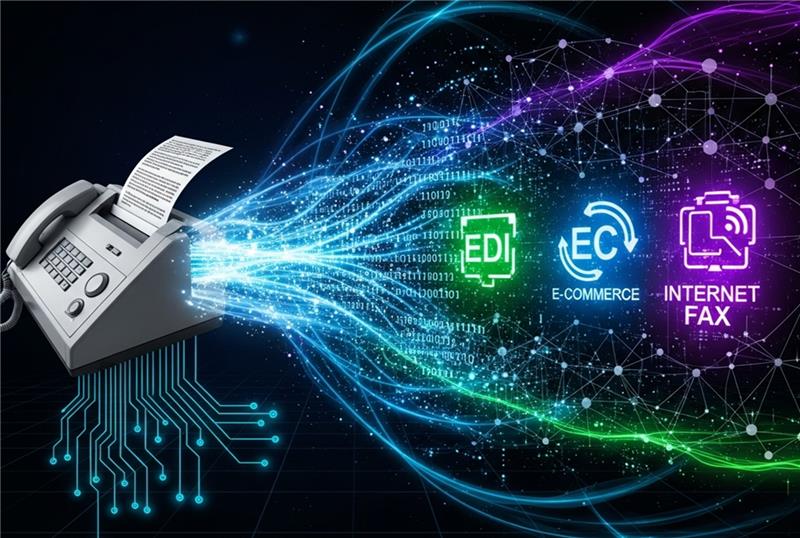
多くの企業が業務の効率化や省力化、コスト削減、環境への配慮なを理由に「FAXをやめたい」「紙の注文書や発注書の処理をやめて業務を効率化したい」としながらも、今でも日常的に使われています。
とくに受発注業務においては、長年行ってきた業務を変えられない、取引先がFAXしか対応してくれないなどの理由から、切り替えられないという現実があります。
本コラムでは、日本のビジネスシーンにおけるFAXの現状や、受発注業務でFAXが今でも必要な理由、そして、FAXを完全にやめることが難しくても「効率化」するための実践的な方法について解説していきます。
日本の商慣習におけるFAX利用状況
日本企業におけるFAXの使用率は年々減少しているものの、デジタル化が進んだ今なお非常に高い水準にあります。
とくに中小企業を中心に、注文書や発注書のやり取りがFAXで行われることが多く、受発注業務における重要な手段として根強く利用されています。
「FAXをやめたいのにやめられない」いちばんの理由が「取引先がFAXを希望するためやめられない」です。
つまり、自社の意向だけではFAXからの脱却が難しいのが現状なのです。
とくに注文書・発注書という形式がある書類においては、「書面で証跡を残す」「手書きでの修正ができる」といった特長が、FAXをやめられない大きな理由にもなっているのです。
参考:株式会社帝国データバンク「「経営診断ツールの認知・活用状況及び、決済・資金調達の実態に関する調査」調査報告書」
FAX以外で受発注を行う方法とは
では、FAX以外で受発注を行う手段にはどのような方法があるのでしょうか?
ここでは、代表的な2つの方法を紹介します。
EDI(Electronic Data Interchange)
EDIは、企業間で注文書や発注書などの商取引データを電子的に交換する仕組みです。
取引先とのデータを標準化されたフォーマットで直接やり取りできるため、FAXや手入力による作業の手間を大幅に削減できます。
受発注業務においては、EDIを導入することで「自動で注文データが基幹システムに反映される」「人為的なミスが減る」「処理速度が格段に上がる」といったメリットが期待されます。
EC(BtoB電子商取引)
BtoB向けのECサイトを活用する方法も有効です。
企業は発注をECサイト上で行い、注文情報がデジタルで一元管理されるため、書類のやり取りが不要になります。
とくに継続的な取引がある企業にとっては、定期注文や履歴からの再注文など、業務効率化に直結する機能が多くあります。ECは中小企業でも導入がしやすく、クラウド型のサービスが広く提供されています。
なぜFAXでの受発注をやめられないのか
FAX以外の受発注手段があるとはいえ、すぐに移行できない理由も明確に存在します。
ここでは、FAX文化が根強く残る背景を整理します。
業務内容見直しの負担
EDIやECを導入するには、現在の業務フローを見直し、システムに合わせた変更が必要です。
とくに注文書や発注書のフォーマット変更、社内手続きの再整備は時間と労力を要します。
現場の従業員から「今のやり方で不自由していない」と反発を受けることもあり、経営層が推進しようとしても現場で止まるケースもあります。
手書きの利便性
FAXが支持される理由のひとつに、「手書きの柔軟性」があります。
注文書に手書きで「至急対応願います」「納期変更」などのメモを追記できる点は、アナログならではの強みです。
こうした利便性が、デジタル化によって失われることへの抵抗感も無視できません。
取引先の意向
自社がFAXの廃止を望んでいても、取引先がFAXを希望すれば、やめることは難しくなります。
とくに大手企業や長年の取引先の意向を無視することはできず、「FAXを続ける必要がある」という決断になるケースもあります。
コスト面の問題
EDIやECなどのシステムを導入するには、初期費用や運用費がかかります。
中小企業にとって、このコストが大きな障壁となります。
とくにFAX送信にかかるコストが小規模で済んでいる企業ほど、費用対効果が見合わないと判断しがちです。
ITリテラシーの不足
現場で働く従業員のITリテラシーが低い場合、新しいシステムの導入は大きな負担になります。
パソコンの操作やクラウドサービスの利用に不慣れなスタッフが多いと、教育・サポートの体制も求められます。
効率的にFAXで受発注業務を行うには
FAXを完全にやめることは難しいとしても、「FAXを使いながら業務を効率化する」方法は存在します。
ここでは、FAXによる注文書・発注書の受信・送信それぞれの場面において、業務改善に寄与するツールや仕組みを紹介します。
注文書や発注書などをFAXで送信をする場合
インターネットFAX
インターネットFAXは、パソコンやスマートフォンなどでクラウド上からFAXの送受信を行うサービスです。
紙を印刷してFAX機にセットする必要がなく、PDFなどのデジタルファイルをそのまま送信できます。
注文書や発注書をPCで作成・保存し、FAX番号宛にペーパーレスで送信できるため、業務時間を大幅に短縮できます。
また、送信ログの管理や再送信も簡単です。
自動帳票送信サービス
大量の注文書や発注書を複数の取引先に送る場合には、自動帳票送信サービスの導入が有効です。
基幹システムと連携して、定型フォーマットで出力された帳票を自動でFAX送信する仕組みです。
これにより、担当者が一件ずつ手動でFAXを送る必要がなくなり、ミス防止・作業時間短縮につながります。
注文書や発注書などをFAXで受信をする場合
受信した内容をテキスト化するAI-OCR
FAXで受信した注文書や発注書の情報を、自動でテキストデータに変換するAI-OCR技術が進化しています。
手書き文字の認識精度も向上しており、実用レベルの精度を実現しています。
これにより、FAXで届いた情報を手入力する作業時間の削減が可能です。
RPAの導入
AI-OCRでテキスト化された注文情報を、基幹システムや在庫管理システムに自動で入力するには、RPA(Robotic Process Automation)が活用できます。
人手を介さずにデータ入力を自動化することで、受発注業務の負担を大幅に軽減できます。
自動FAXとRPAの組み合わせは、FAX文化を残しつつ、内部の業務をデジタル化する最良の方法といえます。
まとめ
FAXによる注文書や発注書のやり取りは、日本の受発注業務に深く根付いた慣習です。
EDIやECなどの選択肢があるとはいえ、完全に移行することは現実的に難しいのが現状です。
だからこそ、今は「FAXを使い続けながら、いかに業務を効率化するか」という視点が重要です。
インターネットFAX、AI-OCR、RPAなどの技術をうまく組み合わせれば、FAXの運用を残したままでも大幅な省力化が可能です。
FAXをやめられないからといって、非効率なままでいる必要はありません。
業務効率化の一歩を、FAX活用の見直しから始めてみてはいかがでしょうか?